 「てんかん診療のお作法」 「てんかん診療のお作法」
〜 てんかん診療に関して一言 〜
 ヒント19: ヒント19:
「抗てんかん薬の薬理作用の検討は、
薬物作用学的視点だけではなく、
薬物動態学的視点も必要」
|
ディーター・シュミット先生の書かれました単行本『抗てんかん薬の有害作用』(抗てんかん薬という特殊な薬剤の副作用だけで、1冊の本が書けてしまうということ自体がすごいことなのですが)の総論で、薬理作用を概観する箇所があります。
薬理作用のメカニズムを各種要因に分けて考える章で、まず「薬理学的要因」と「臨床的要因」とに大きく分け、薬理学的要因を、さらに「薬物作用学的要因」「薬物動態学的要因」「薬物調剤学的要因」に分類しています。
箇条書きにしますと、
1.薬理学的要因(Pharmacological Factors)
1)薬物作用学的要因(Pharmacodynamic Factors)
2)薬物動態学的要因(Pharmacokinetic Factors)
3)薬物調剤学的要因(Pharmaceutical Factors)
2.臨床的要因(Clinical Factors)
となります。
薬物作用学的要因というのは、薬物が身体、標的臓器や病原体にどのように作用するか、を考えるものです。
薬物動態学的要因は、その逆で、薬物が身体からどのような影響を受けるか、例えば、肝臓の解毒作用や腎臓の排泄作用などの影響を考えるものです。
薬物調剤学的要因には、シロップ剤か粉薬か錠剤か、腸溶剤や徐放剤か、といった要素があります。
臨床的要因は、睡眠・覚醒リズムが安定しているか、便秘傾向か下痢傾向か、食欲はあるかないか、年齢は、体重は、といったものです。
「抗てんかん薬による治療は、臨床発作に対する対症治療で、発作型毎に、有効薬剤が決まってくる。」(→ヒント5)というのは、薬物作用学的要因から考えた理論です。
通常の急性疾患では、効果(あるいは副作用)発現の速い薬剤を使用することになり、この薬物作用学的要因だけで、事足りる場合が多いのですが、慢性疾患の場合は、他の要因にも配慮する必要性が高くなってきます。
急性疾患の治療のように、薬剤が、初回投与の段階で、有効濃度に達し、1回だけでも、それなりに効果を発揮するというものであれば、薬物作用学的要因だけで薬剤選択をしていても、それ程大きな間違いは起こさないかもしれません。
しかし、慢性疾患の場合は、すぐに決着がつく薬剤というよりは、長期服薬していて、定常状態(血中濃度が安定し、濃度の変動幅が日内変動に限られる状態)に達し、その濃度が有効濃度を越えて、始めて効果が期待できます。(→ヒント7)
また、他の併用薬剤との相互作用によっては、期待通り効かなかったり、効き過ぎたりする場合も出てきます。
このように、薬剤の単なる効能だけではなく、薬剤が周囲の環境(併用薬剤も含む)からどのような影響を受けるか、を考慮するのが、薬物動態学的要因を検討する、ということになります。
定常状態一つをとっても、抗てんかん薬の場合は、速いものでも1週間、遅いものでは、1ヶ月間かかる場合があります。
しかも、眠気を来しやすい薬剤では、有効濃度を期待できる投与量を、最初から投与するわけにはいきません。
四段階ぐらいに分け、慣らし慣らし徐々に増量していきます。
当然1剤の効果を診るだけでも、数ヶ月から半年ぐらいかかる場合が出てきます。
患者さんも、患者さんのご家族も、主治医も、使用する抗てんかん薬の薬物動態学的特徴を共通認識していないと、この長期の日数には耐えられず、正しい治療は不可能となります。
薬物動態学的に薬理作用を認識しておく、ということは、抗てんかん薬治療の“お作法”の中でも、非常に重要な要素の一つだと思います。
この項終了
平成19年8月10日(金):公開
岐阜のてんかん専門クリニック、なかむらクリニック:提供
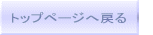
|