 「てんかん診療のお作法」 「てんかん診療のお作法」
〜 てんかん診療に関して一言 〜
 ヒント74: ヒント74:
「診断が“てんかん”止まりでは、
ちょっと心配」
|
以前に「正しいてんかん診療とは」という文章を書きました。
正しいてんかん診療を受けておられるか否かの目安として、21の吟味項目を箇条書きにしたものでしたが、小難しいとあまり評判が良くありません。(→「正しいてんかん診療とは」)
そこで、今回、もっと簡単な見極め方を書きます。
それは、診断が「てんかん」で止(とど)まっているか否かです。
「てんかん」と診断されているということは、「問題の症状(これは、痙攣だったり、単純な幻覚だったり、意識障害だったりしますが)は、脳に原因があるらしいよ」ということを表現しているだけです。
「どういうてんかんなのか」ということが診断されていませんと、発作が止まりやすいのか難しいのか、知的障害を合併しやすいのか心配しなくても良いのか、将来服薬は止めることができるのか否か、といったことが予測できません。
レースで、ゴールが見えないだけではなく、方向も判らないまま、走り出すようなものです。
また、抗てんかん薬によるてんかん治療は、「てんかん発作に対する対症治療」ですから、治療の標的とする「発作型」が診断されていませんと、治療薬を選ぶことができないことになります。(→ヒント5)
対症治療というのは、標的がずれていますと全く意味をなしません。
例えば、胃腸風邪の時に、解熱剤を使っても、下痢は治まりませんし、咳の風邪の時に、鼻水用の抗ヒスタミン剤をのみますと、のどが乾燥して、却って咳はひどくなります。
風邪でしたら、長くても1週間程で治まりますので、笑い話で済みますが、てんかんの治療は、5年、10年、患者さんによっては一生服薬することにもなりますので、標的(発作)の確認は、正しい治療を受けられるには、必須の条件となります。
そこで適切なてんかん診療を受けておられることを確認する最低限の必要条件は、
一つは、「どういうてんかんか」が診断されていること。
具体的には、診断が「てんかん」止まりではなく、「○○てんかん」と診断名が付いていることです。
もしくは「□□てんかん」が疑わしい、と言われていることです。
もう一つは、「どういう発作型か」が診断されていることです。
欧米の権威者の中には「脳波だけで診断ができるてんかんは、欠神てんかんだけ」と言う人がいるぐらい、てんかんの診断には、脳波検査以上に発作症状(発作表出)の吟味が重要です。
発作型の診断ができていませんと、てんかんの診断も、治療薬の選択も曖昧なものになってしまいます。
やはりこの「何々てんかん(てんかん類型)」と「何々発作(てんかん発作型)」の2つの診断が付いていないとなりますと、適切なてんかん診療を受けているとは言い難いのではないでしょうか?(→ヒント51)
この項終了
平成22年4月18日(日):公開
岐阜のてんかん専門クリニック、なかむらクリニック:提供
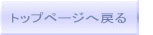
|