 「てんかん診療のお作法」 「てんかん診療のお作法」
〜 てんかん診療に関して一言 〜
 ヒント85: ヒント85:
「てんかん診療は、人生設計の中で考える」
|
てんかんの治療には、長期間を要します。
それは、誤診や過剰診断がない限り、多くは10年間以上に及びます。
そのため、就学・就職・結婚、女性であれば妊娠・出産など、社会的役割機能(社会から求められる役割)に応じて、配慮が必要になります。
例えば、幼児期早期の発病で、最初のうちは、誘因として、発熱や下痢・嘔吐、風邪薬や喘息治療薬の服用などが考えられ、発作頻度が少なく、状況関連性発作(機会発作)かてんかんかハッキリしない場合を考えてみましょう。(
→ ヒント2、ヒント15、ヒント50、ヒント52 )
この段階では、親御様は、発作があるたびに、発作直後は「すぐに治療を開始しよう」と思い、1週間もすると、「今回が最終発作かもしれない」という考えが出てきて、なかなかてんかんとしての治療開始に踏み切れません。
その場合、未治療で経過を診ることになるのですが、延々と経過観察を続けるわけにも行かず、いつ頃を最終期限とするか、という問題が出てきます。
その場合、「就学時検診」が、Xデーになります。
多くの自治体では、「年長」幼児期の秋に実施されます。
親御様の人情では、小学校に入るための就学時検診で、余計なことは言いたくないという思いが強いでしょうから、それまでには、抗てんかん薬処方が確定して、臨床発作が消失していなければなりません。
そうなりますと、抗てんかん薬処方の調整には、順調に行っても半年間ほどはかかりますので、逆算して、「年中」の1〜3月か、「年長」の4月には、治療開始を決めなければなりません。
逆に、幼児期早期の発病で、状況関連性発作かてんかんかハッキリしないが、親御様の不安が強く、早期治療開始を決断された場合を考えてみましょう。
この場合、親御様のお気持ちには「本当はてんかんではないのでは?」という思いが強いので、小児科医のよく言う「3年理論(3年間発作が出なければ治っているという楽観論)」に従い、通常の熱性けいれんと同様に、小学校に入ったら、服薬を中止しようとされる場合が多いようです。
しかし、小学1〜2年生は、身体的にも精神的にも、環境に馴染めず、不調を来すことが少なくないのです。
このような不安定な時期に、「抗てんかん薬の減量・中止」という大仕事を、わざわざぶつけることは避けた方が賢明でしょう。
小学3年生まで待って、実施されることをお勧めします。
次のXデーは、「修学旅行」ですが、多くの学校では、その1年前に「校外学習」とか「宿泊学習」と呼ばれるものがありますので、小学5年生頃となります。
その頃には、抗てんかん薬処方が安定して、ご自分で服薬管理ができるようになっているのが理想です。
当院では、患者さんが女の子の場合、「修学旅行」が終わったら、葉酸製剤(将来妊娠した際の胎児奇形予防のための薬剤)併用服用の検討に入ります。(修学旅行中は、なるべくシンプルな処方にしておきたいですからね)
また、女の子の場合、将来の不妊症を回避するためにも、この頃には、卵巣機能に影響を与える可能性のある薬剤は、できれば処方から抜いておきたいところです。
そこで、乳幼児期から投薬が始まった薬剤の吟味が必要になりますので、「初潮」が重要なXデーになります。
受験や進学については、人それぞれですので、何とも言えませんが、昔から「長期にわたる寛解期間が得られている場合には、可能であれば、就労までに、減量・中止を試すべき」と言われています。
そこで、次のXデーは、「就労」」です。
しかし、抗てんかん薬中止の評価には、月日を要しますので、就労直前は避けるべきでしょう。
また、就労直後も避けるべきでしょう。
理由は、小学1〜2年生を避けるのと同じで、心身ともに環境に馴染むのに時間がかかるからです。
減量・中止を試すのは、就労後3年以上が経過して、発作が再発して急に休みを取ることになっても、失職しないだけの人間関係と職場における位置づけを確保しておく必要があります。
「結婚」と「妊娠」に関しては、女性の場合、直前ではなく、ある程度期間の余裕を持って、可能であれば、薬剤数も投与量もできるだけ減らし、葉酸製剤の併用服用を連日にするなどの配慮が必要になります。
最後のXデーは、「退職」です。
特発性全般てんかんの「若年性ミオクロニーてんかん」や「覚醒時大発作てんかん」は、発作寛解は得られやすいものの、生涯にわたる服薬を覚悟しなければならない、と言われています。
と言いましても、20〜30年間以上発作が消失していますと、断薬が可能か確認してみたくなるのは人情です。
その場合、職業人である間は、社会人の責任として、服薬を継続するが、退職して60代になって、減量を試される方が多いと聞いています。
以上、簡単に見てきましたが、抗てんかん薬は「人生を守るためのお薬」という言葉があるぐらいですので、ご自分の人生設計の中で、人生の妨げにならないように、お使いいただくのが宜しいか、と思います。
この項終了
平成24年3月5日(月):公開
岐阜のてんかん専門クリニック、なかむらクリニック:提供
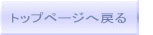
|