 「てんかん診療のお作法」 「てんかん診療のお作法」
〜 てんかん診療に関して一言 〜
 ヒント81: ヒント81:
「再考:抗てんかん薬治療」
|
てんかんは、100〜200人に1人のよくある病気ですが、その症状の特殊性から、多くの誤解がある病気でもあります。
前回の「診断」編に続いて、今回は、治療に使う「抗てんかん薬」について、少しお話をさせていただきます。
抗てんかん薬は、普段我々が使用する風邪薬や頭痛薬とは異なった使い方をする薬剤で、いくつかの特徴があります。
1.てんかん発作に対する対症治療
病気の治療は、原因治療と対症治療に分けられますが、抗てんかん薬は、てんかん発作に対する対症治療のお薬です。標的にする発作型が確認されていませんと、闇雲に薬剤選択をしていることになります。(→ヒント5)
2.未来の発作に対する予防治療
通常の対症治療では、解熱したり頭痛が治まったり、問題にしている症状が軽減あるいは消失したら、服薬を止めてしまいますが、抗てんかん薬の場合は、明日出るはずだった発作を来週に、来週出る予定だった発作を来月に「先送り」する予防薬ですので、発作症状がないときに黙々と飲み続けなければなりません。(→ヒント16)
3.血中濃度を安定させて効かせる
毎日欠かさず服薬して、薬剤の血中濃度を安定させて、効かせるお薬ですので、のんですぐに効くわけではありません。通常1〜2週間、薬剤によっては約1ヶ月間が経過して効果を発揮するものもあります。ですから「副作用は服薬直後から、効き目は忘れかけた頃から」という言葉があるくらいです。(→ヒント7)
4.年単位の長期服薬
通常、服薬は10年間以上になります。病状によっては、生涯にわたる服薬が必要となる場合もあります。そのため「薬剤選択は効き目の強い順よりも、副作用の少ない順に」という考え方もあります。(→ヒント6)
5.3分の2は発作が止まる時代に
3分の2の患者さんは発作が止まるようになったと言われますが、今後新規抗てんかん薬の使用が増えれば、この数字も更なる改善が期待できます。(→ヒント9)
6.基本は単剤治療
抗てんかん薬は、相互作用が顕著な薬剤です。併用すると足を引っ張り合ったり、組み合わせによっては「発作誘発剤」に豹変する場合もあります。「抗てんかん薬の処方調整は、探偵が犯人の可能性もある推理小説を読み解くようなもの」とも言われます。(→ヒント36、ヒント37)
7.個人差が大きい
「てんかんの種類は患者さんの数だけある」と言われるように、非常に個人差が大きいので、オーダーメイド(テーラーメイド)の処方調整が必要になります。(→ヒント1)
「治療ガイドラインは、目安であって、ゴールではない」ということで、ガイドラインに従った治療をしていればよいというわけではありません。
ガイドラインに、その患者さん専用の配慮をどれだけ付加できるかが、“医師の腕前”ということになります。(→ヒント70、ヒント73)
以上のような特徴のため、「お作法」をわきまえた治療を受けませんと結果が出ません。担当医とじっくり時間をかけて話し合われ、「納得」のいく治療を求められるべきでしょう。
この項終了
平成23年12月2日(金):公開
岐阜のてんかん専門クリニック、なかむらクリニック:提供
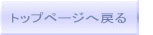
|